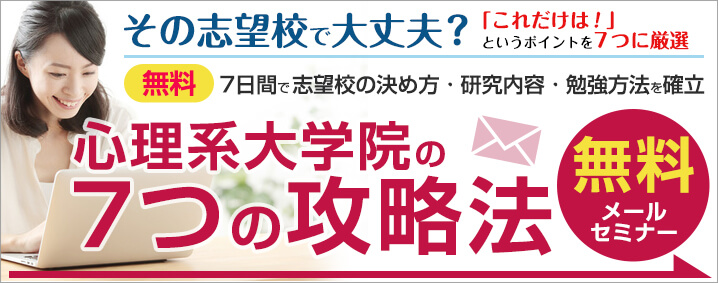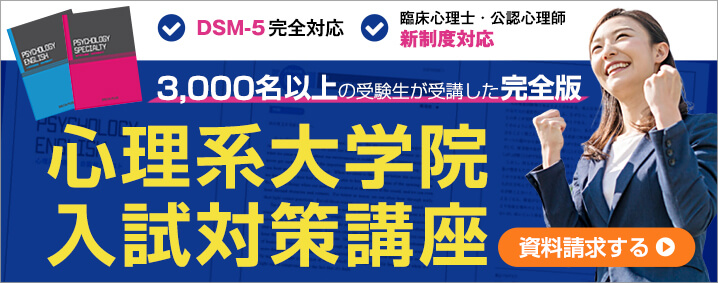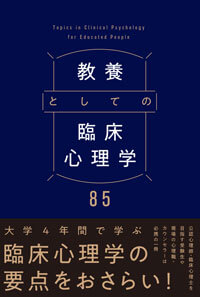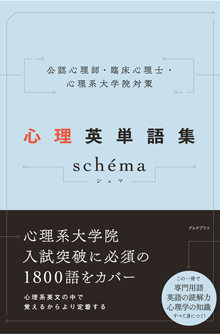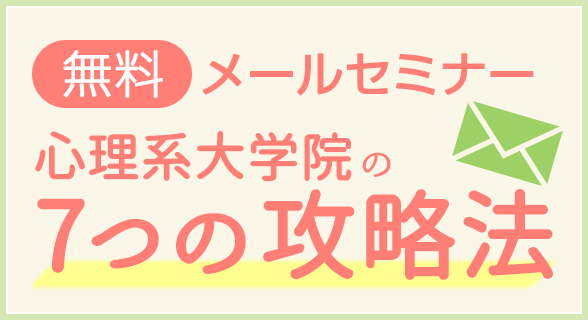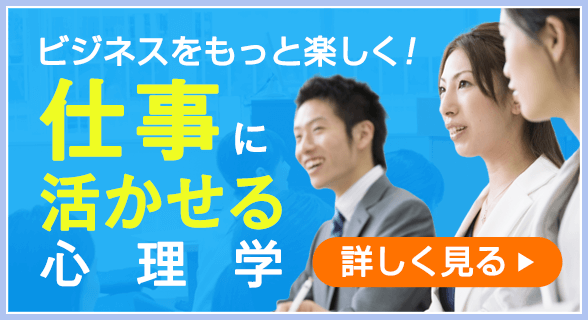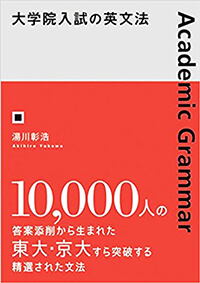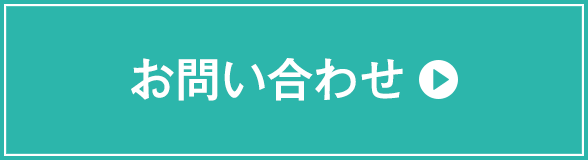生活習慣病の定義
生活習慣病は、食生活や運動、喫煙、飲酒などの日々の生活習慣が発症や進行に深く関与する疾患群です。
代表的なものには、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心疾患、脳血管疾患などが挙げられます。
かつては、加齢に伴い発症しやすいと考えられていたことから成人病とよばれていましたが、生活習慣との関連が明らかになったため、1996年頃から生活習慣病という名称が用いられるようになりました。
生活習慣病には、加齢だけでなく若年期からのライフスタイルが大きな影響を及ぼすことが明らかになっています。
若い世代にも発症する可能性がある疾患群でもあり、発症しなくても早期から予防に務めることが重要です。
現代社会では、食生活の欧米化や運動不足、食事量や栄養バランスの偏りといった生活習慣の変化により、内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)の患者が増加しています。
内臓脂肪が蓄積されることで、脂質異常や高血糖、高血圧などのリスク因子が重なりあい、動脈硬化をはじめとする重篤な疾患へとつながる危険性が高まる状態を指します。
内臓脂肪が過度に蓄積されると、血圧を上昇させるアンジオテンシノーゲンや、インスリン分泌を低下させるTNF-αといった、生活習慣病を招く物質が増加します。
また、動脈硬化を防ぐアディポネクチンや、食欲を抑制するレプチンといったホルモンが減少することで、生活習慣病の発症リスクが高まります。
初期には自覚症状がほとんどありませんが、放置すると血糖値や血圧などの異常が進行し、倦怠感や動悸、体重減少といった症状が現れることがあります。
さらに進行すると動脈硬化が進み、糖尿病や心筋梗塞、脳卒中などの重篤な疾患に発展する危険性が高まります。
生活習慣病の関連キーワード
- ライフスタイル
- 内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)
- 行動変容ステージモデル
- 前関心期
- 関心期
- 準備期
- 実行期
- 維持期
- 特定健診・特定保健指導
生活習慣病の補足ポイント
生活習慣病の予防や治療においては、食事療法や運動療法を中心に、必要に応じて薬物療法も行われますが、根本的な解決には日々の生活習慣やライフスタイルの改善が不可欠です。
例えば、適度な運動、バランスの良い食事、十分な休養、禁煙、節酒などが推奨されています。
しかし、生活習慣の改善が大切だとわかっていても、それを毎日長期間にわたって続けることは、難しいと感じる人が多いのも事実です。
生活習慣病の予防や治療において、患者自身が生活習慣を見直し、継続的に改善していく行動変容を支援していくことが重要になります。
行動変容を起こすためには、医療従事者が生活指導を行うだけでは十分ではありません。
患者が自らの健康状態と共に、生活指導の内容を十分に理解し、主体的にセルフケアに取り組めるように促していくことが求められます。
人が生活習慣に関する行動を変える過程を分類したプロチャスカ, J. O.の行動変容ステージモデルでは、前関心期、関心期、準備期、実行期、維持期の5段階に分けられ、それぞれの段階にあわせた支援が効果的とされています。
前関心期は、当事者がまだ行動を変えようとは思っていない段階であり、関心期は6ヶ月以内に行動を変えようと考えている段階であり、準備期は1ヶ月以内に行動を変えようと考えている段階です。
そして、行動を変えてから6ヶ月未満が実行期、6ヶ月以上が維持期です。
これらの段階は逆戻りしてしまうこともあるため、支援者が患者の取り組みを見守り、動機づけを高め、健康的な行動を維持する自信を持てるように、できていることを称賛するといったことも非常に重要なアプローチです。
| ステージ名 | 概要 | 行動の特徴 | 支援のポイント |
| 前関心期 | まだ行動を変えようと思っていない段階 | 行動変容への関心なし | 情報提供、リスクやメリットの啓発 |
| 関心期 | 6ヶ月以内に行動を変えようと考えている段階 | 行動変容への関心あり | 行動のメリット・デメリットの整理、動機づけ |
| 準備期 | 1ヶ月以内に行動を変えようと考えている段階 | 具体的な計画や準備を始める | 目標設定、行動計画の作成、実行へのサポート |
| 実行期 | 行動を変えてから6ヶ月未満の段階 | 新しい行動を実践し始めている | 継続への支援、成果のフィードバック |
| 維持期 | 行動を変えてから6ヶ月以上が経過した段階 | 新しい行動が定着しつつある | 継続の励まし、再発防止のサポート |
法律面では、2008年からは生活習慣病予防のための特定健診・特定保健指導が制度化され、40歳から74歳を対象に内臓脂肪型肥満に着目した健診と、それに基づく保健指導が義務づけられています。
健診の結果に応じて、動機づけ支援や積極的支援といった段階的な指導が行われ、患者の行動変容を促します。
保健師や管理栄養士による個別面談やグループ指導、さらにはメールや電話でのフォローアップなど、さまざまなセルフケア支援が提供されています。
生活習慣病は初期には自覚症状が乏しいことが多く、気づかないうちに病状が進行してしまうケースも少なくありません。
そのため、定期的な健康診断による早期発見と、異常値が見つかった際の早期支援が極めて重要です。
早期に対応することで、重篤な合併症の予防や、生活の質の維持につながります。