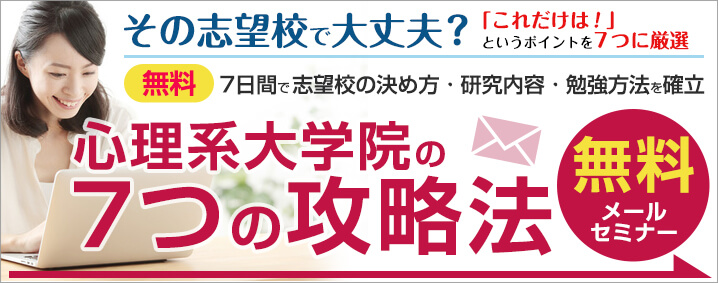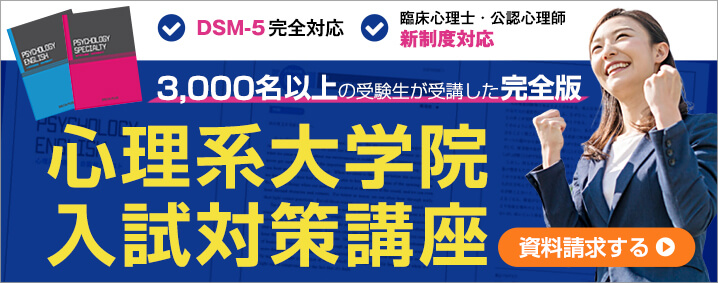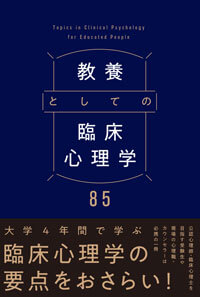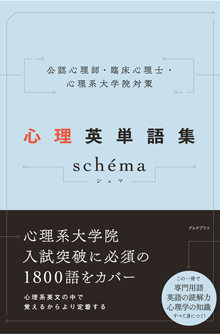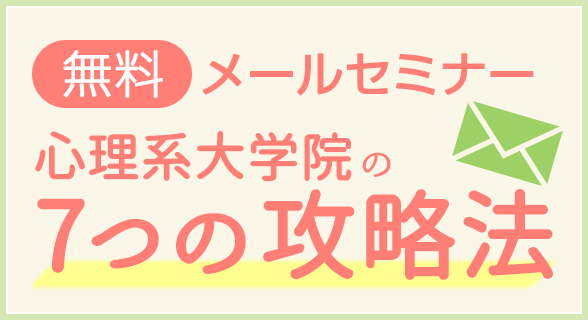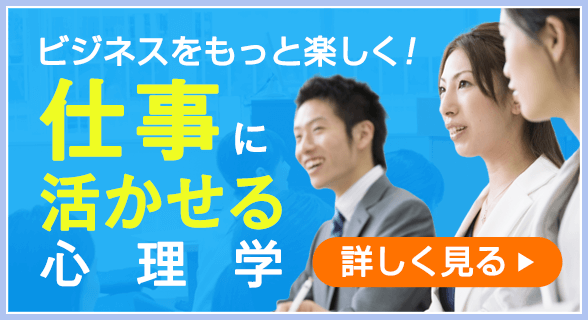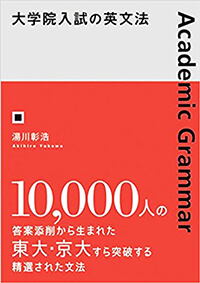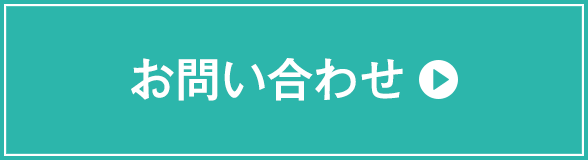保護観察制度の定義
保護観察とは、罪を犯した人や非行のある少年が、保護観察所の指導を受けながら、社会の中で更生できることを目指す制度です。
保護観察処分を受けた人は、刑務所や少年院などの施設に収容されるのではなく、自宅などに戻ってそれまでと同様の社会生活を続けていきます。
そして、保護観察期間中は、保護観察官や保護司による定期的な面談、指導と支援を受けながら再犯防止や社会復帰を目指します。
施設などに入所して矯正教育を施すことを施設内処遇とよびますが、それに対して保護観察は社会内処遇とよばれます。
保護観察は、犯罪や非行の程度が深刻でない場合や、本人が社会の中で更生する可能性が高い場合に選ばれます。
また、保護観察は、対象者の立場や経緯に応じて4つの種類に分けられています。
家庭裁判所の少年審判で保護観察処分を受けた非行少年は1号観察、少年院での矯正教育を経て、仮退院を許された少年は2号観察とよばれます。
そして、刑務所などの刑事施設から仮釈放された成人や少年は3号観察、刑事裁判で執行猶予付き有罪判決を受けた者のうち、特に再犯防止や生活指導が必要とされた場合に保護観察が付された者は4号観察となります。
| 種類 | 対象者・内容 |
| 1号観察 | 家庭裁判所の少年審判で保護観察処分を受けた非行少年 |
| 2号観察 | 少年院での矯正教育を経て仮退院した少年 |
| 3号観察 | 少年院での矯正教育を経て仮退院した少年 |
| 4号観察 | 執行猶予付き判決で保護観察が付された者 |
保護観察制度の関連キーワード
- 保護観察
- 施設内処遇
- 社会内処遇
- 保護観察官・保護司
- 指導監督
- 補導援護
- 一般遵守事項
- 特別遵守事項
保護観察制度の補足ポイント
保護観察は、家庭裁判所や刑事裁判所、あるいは仮釈放や仮退院の場面で決定されます。
例えば、少年事件の場合、家庭裁判所が少年の非行の内容や更生の可能性を考慮し、施設に収容する必要がないと判断したときに保護観察が選択されます。
成人の場合は、刑事裁判で有罪となった場合に執行猶予が付され、その際に保護観察が付されることがあります。
保護観察が決まると、その処分を受けた人は、まず保護観察所で担当の保護観察官が決まり、その後、地域の保護司が担当として指名されます。
保護観察官は法務省の国家公務員であり、心理学や社会学の専門知識を生かして支援計画の策定や、重大な規律違反時の対応など、専門的・統括的な役割を担います。
保護司は非常勤の国家公務員(民間ボランティア)であり、地域に根ざした日常的な指導・支援や生活状況の把握を担当します。
この両者が協力して、対象者の更生を支えていきます。
その後、保護観察対象者は月に1~2回、保護司に生活状況を報告したり、悩みを相談したりしながら日常生活を送ります。
また、保護司が対象者の自宅を訪問することもあります。
なお、薬物犯罪や性犯罪など特定のケースでは、保護観察官による再犯防止プログラムを受けることもあります。
保護観察を受けている間は、社会生活を続けながら指導監督と補導援護を受けます。
指導監督では、学校や仕事にきちんと通っているか、約束を守れているかなどを確認し、問題があれば注意や助言をします。
補導援護では、就労や就学の支援、生活相談、家族関係の調整など、社会復帰を後押しするためのサポートが行われます。
保護観察期間中は、必ず守るべき事項として一般遵守事項と特別遵守事項があり、これに違反した場合は警告や保護観察の取り消し、場合によっては少年院や刑務所に戻されたり、新規に収容されたりすることもあります。
一般遵守事項は、保護観察中のすべての対象者が守るべき基本的なルールです。
主に、定められた住居に居住し、定期的に保護観察官と面談し、善良な生活態度を保つことなどが含まれます。
特別遵守事項は、個々の事情や再犯防止のために、裁判所や保護観察所が追加で定める特別なルールです。
例えば、特定の場所への立ち入り禁止や、特定の人物との接触禁止、アルコールや薬物の使用禁止などが挙げられます。
| 一般遵守事項の例 | 定められた住居に居住する |
| 定期的に面談を受ける | |
| 善良な生活態度を保つ | |
| 特別遵守事項の例 | 特定の場所への立ち入り禁止 |
| 特定の人物との接触禁止 | |
| アルコールや薬物の使用禁止 |
保護観察の期間は対象者や処分の種類によって異なり、成人の場合は裁判で言い渡された期間、少年の場合は原則20歳に達するまでなどが一般的です。
ただし、少年が保護観察処分となった時点から20歳に達するまでの期間が2年未満の場合は、2年間の保護観察期間が設けられます。
社会内処遇は本人の自尊心や自己効力感を損なわず、社会への適応を促す効果があると考えられています。
それに対して施設収容による隔離は、本人の心理的負担が大きく、社会復帰が難しくなるリスクもありますが、保護観察はそのリスクを軽減できる可能性が高いと言えます。
どちらの処遇であっても、対象者を無理やり更生させるような関わり方はあまり有効ではなく、本人の心理面への配慮も重要です。
そのため、保護観察官には心理学や教育学、社会学などの幅広い専門知識を生かして、対象者の特性や心理状態に応じた指導を行う力が求められます。