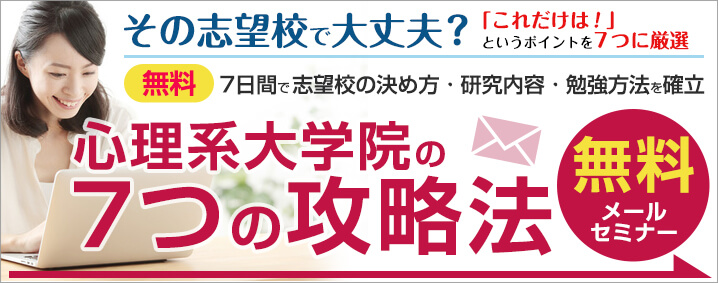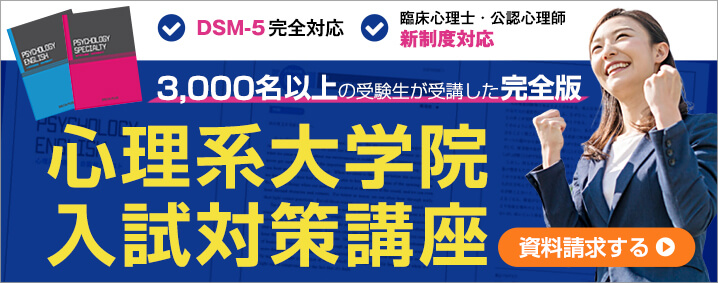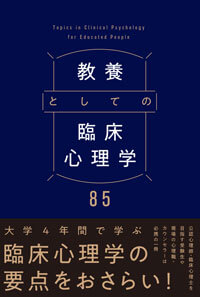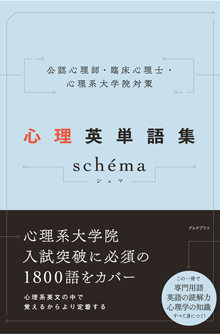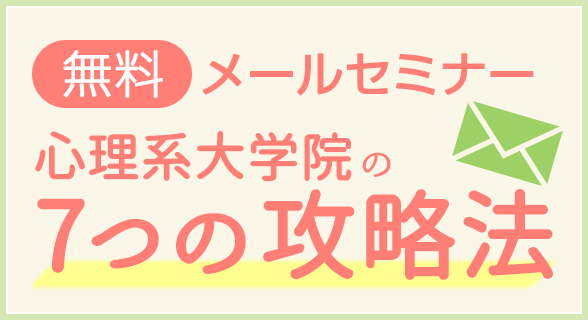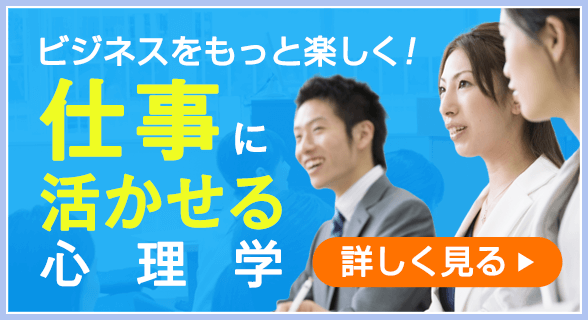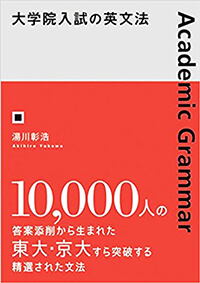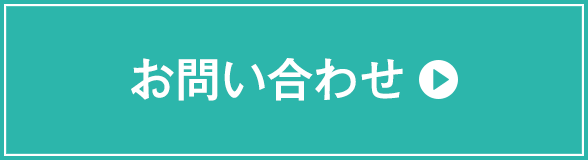解離症の定義
解離症(解離性障害)とは、解離や離人感と呼ばれる症状を特徴とする疾患群のことです。
解離とは、意識、記憶、自己像などの、本来は統合されているべき精神機能が、部分的あるいは全体的に統合されない状態を指します。
この概念は、19世紀後半に、シャルコー, J. M. により概念化されました。
解離は、心的外傷となるような大きなストレスから無意識に自己を守るために生じることが多いとされています。
具体的には、強い葛藤に直面して圧倒されたり、それを認めることが困難であったりする場合などに、その体験に関する意識の統合が失われ、知覚や記憶、自分が誰であり、どこにいるのかといった認識などが意識から切り離されてしまう状態を指します。
離人感は、自分の感覚、身体、意志などが自分と切り離されているように感じる症状であり、非常に強いストレスや疲労を経験した際に生じやすい他、てんかんなどの脳の疾患が原因で生じることがあります。
なお、作業に集中している間に名前を呼ばれたがまったく気づかなかった、自分のことを言われているのに他人事のように聞いていたなど、一過性の解離や離人感は誰にでも生じ得ます。
しかし、解離症に至ると、こうした状態が長期間続いて日常生活に支障を来たすようになります。
解離や離人感を呈する疾患としては、自己に関する情報を思い出せない解離性健忘、記憶のみならず自己同一性が断片化してしまう解離性同一症、記憶や現実検討能力は保たれているものの、離人感を示し、現実感が失われたような感覚を体験する離人感・現実感消失症がDSM-5に記載されています。
解離性同一症は、旧版のDSMにおいては多重人格性障害と名づけられていた時期がありましたが、現在では、意識をうまく統合できず、それにより同一性の破綻まで生じている病態として理解されています。
また、解離性健忘の一種として、突然失踪して遠くの土地で発見された人が、どうやってそこまで行ったのか覚えていないという解離性遁走が見られることもあります。
解離性遁走は、DSM-IVでは独立した診断名の1つでしたが、DSM-5においては解離性健忘の症状の1つとして記載されています。
解離症における健忘は、脳損傷などによる健忘や通常の物忘れなどとは区別されます。
解離症の関連キーワード
- 解離
- 離人感
- 解離性健忘
- 解離性同一症
- 離人感・現実感消失症
解離症の補足ポイント
従来、ヒステリーと呼ばれていた病態は、DSM-5では「変換症(転換性障害)」と「解離症」とに分類されています。
解離性障害の原因について、精神分析的立場からは、無意識の葛藤や内的不安が言語化・意識化される代わりに、精神機能の障害に置き換えられると考えられています。
そのため、強いストレスを受けたりすると、変換症に見られるような身体化や、解離などの形で症状が現れると考えられています。
解離症は心的外傷と関連していることが多いため、心的外傷に対する心理療法が解離症の支援においても有効です。
なお、解離症状を示している人が、家庭内暴力を受けるなど現実的な危機にさらされている最中である場合は、まず環境調整を優先して、それから心理的・社会的な支援を行う必要があります。
支援を進めるためには、支援者とクライエントとが信頼関係を築くことが欠かせませんが、心的外傷を経験した人にとってはそれも容易なことではありません。
支援者によって助けられるどころか傷つけられるのではないかと恐れたり、治療費を搾取されるのではないかと疑念を抱いたりすることもあります。
傷つくことに敏感になっているクライエントとは、根気よく丁寧に関係性を構築していくことが、特に重要になります。
抑うつや不安が強い場合などは医療と連携して薬物療法を併用することで症状を和らげたり、EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)を実施したりすることが役立つこともあります。
解離症の治療で使われる技法の1つに、グラウンディングがあります。
これは、クライエントの五感を活用して、自己と世界とのつながりや現実感を強く感じられるようにする技法です。
一例としては、クライエントに両足を床につけて足裏の感覚を感じるようにしてもらいます。
このようにすることは、地に足をつけて自分を支える感覚や、現実感を取り戻すことにつながり、解離状態からの覚醒を促すことに役立ちます。
その他、大きな音量で音楽をかけたり、氷を手で握らせたりすることもあります。