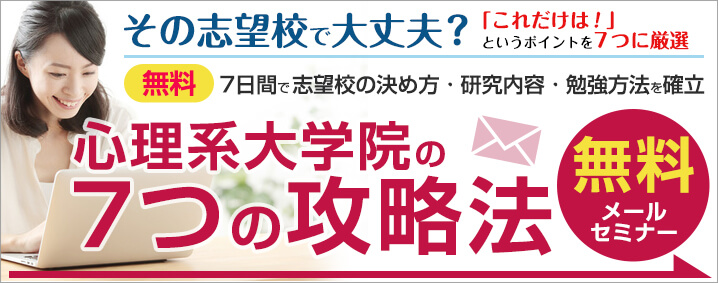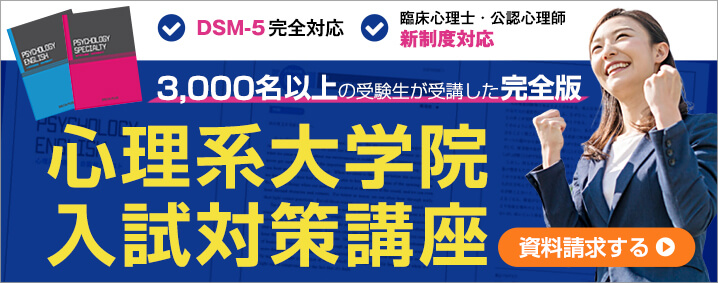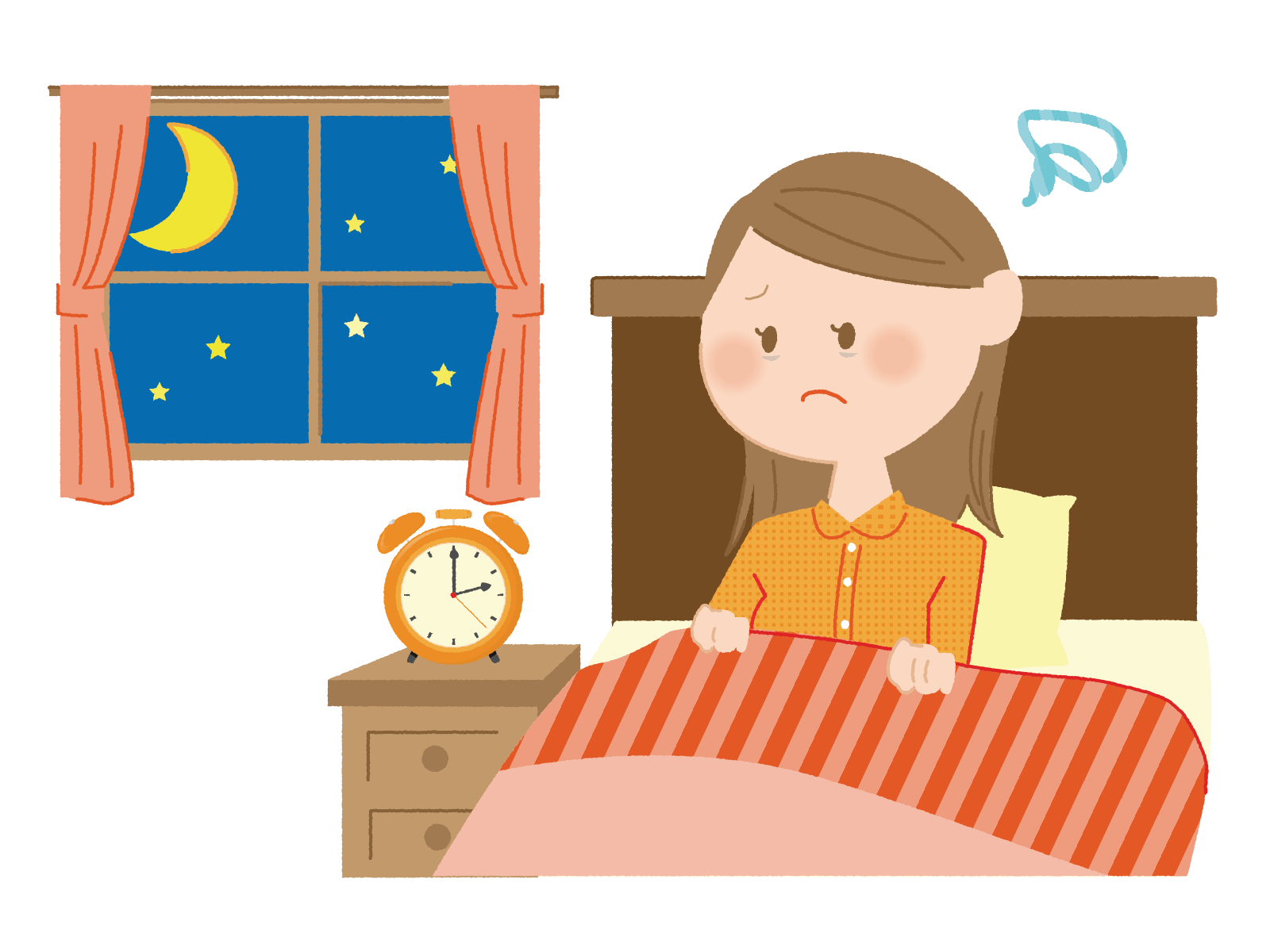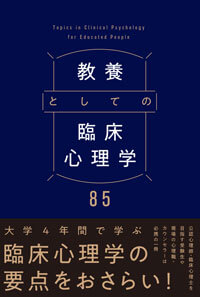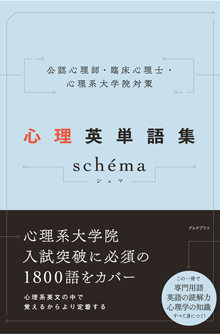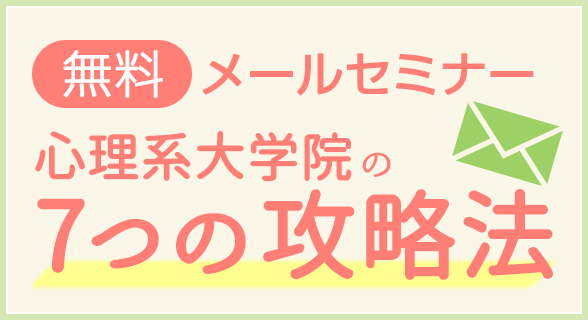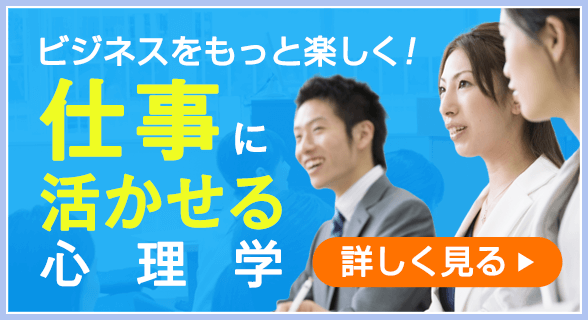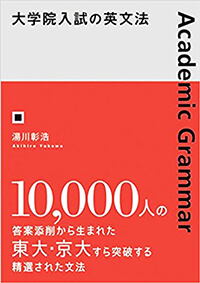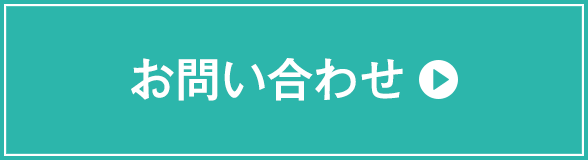双極症の定義
双極症(双極性障害)は以前は躁うつ病ともよばれ、活動が亢進した状態を呈する躁病(軽躁)エピソードと、気分が落ち込んだ状態を呈する抑うつエピソードとの間を揺れ動く精神疾患です。
躁(軽躁)エピソードには、自尊心の肥大、睡眠欲求の減少、多弁、観念奔逸、注意転導性、目標指向性の活動の増加または精神運動興奮、性的無分別や浪費などが挙げられます。
抑うつエピソードには、抑うつ気分、興味または喜びの喪失、体重減少または増加、不眠または過眠、精神運動興奮または制止、疲労感または気力の減退、無価値感または罪責感、思考力や集中力の減退、自殺念慮または自殺企図などが挙げられます。
双極症はDSM-5-TRでは「双極症および関連症群」に含まれ、双極症I型と双極症II型に大別されます。
双極症I型は躁(軽躁)エピソードと抑うつエピソードを繰り返し、双極症II型は軽躁エピソードと抑うつエピソードを繰り返します。
躁エピソードと軽躁エピソードは、症状の重症度や持続期間が異なります。
双極症II型においては、双極症I型よりも抑うつエピソードが長期間見られやすいと言われています。
症状の激しさという点では躁エピソードが見られる双極症I型の方が重症だとしても、人生や全般的な生活に及ぼす影響を考えると、双極症II型が軽症だとは必ずしも言えません。
なお、少なくとも2年間にわたって、そのうち半分以上の期間において軽躁症状や抑うつ症状が見られるものの、躁エピソード、軽躁エピソード、抑うつエピソードのいずれの基準も満たさないものは気分循環症とよばれます。
双極症の関連キーワード
- 躁うつ病
- 躁病(軽躁)エピソード
- 抑うつエピソード
- 双極症I型
- 双極症II型
- 気分循環症
- 躁転
- 急速交代型(ラピッドサイクラー)
双極症の補足ポイント
双極症は躁(軽躁)エピソードと抑うつエピソードを繰り返しますが、躁(軽躁)エピソードが前面に出ている時は活動的でさまざまなことに取り組めるため、問題を自覚できないことがよく見られます。
しかし、抑うつエピソードが表れると本人も日常生活で困難を感じ始めます。そのため、医療機関や心理の専門家を訪れるのは抑うつエピソードを呈している時が多いです。
クライエントの抑うつエピソードを中心とした語りを聴くと、うつ病に該当するように思えることもしばしばありますが、安易にうつ病としての治療や支援を始めるのは注意が必要です。
特に抗うつ薬による治療を行うことで、抑うつエピソードから躁(軽躁)エピソードに移行する躁転が生じることがあります。
双極症において、躁(軽躁)エピソードと抑うつエピソードが併存する混合性の特徴を伴うことがあります。
このような場合、さまざまなアイデアが浮かぶが行動に移せない、すごく落ち込んでいるが色々な行動はできるといったことが見られます。
双極症は自殺の危険性が非常に高い疾患だと言われています。
重度の抑うつエピソードの期間から少し抜け出して行動する力が出てきたときに自殺企図が見られることがあります。
また、混合性の特徴を示しているときはひどく落ち込んで希死念慮が出ると同時に、焦燥感がその気持ちを助長し、さらには実際の行動に移すことができてしまう可能性があるので、特に自殺リスクが高まります。
薬物療法としては、気分安定薬や抗てんかん薬が用いられます。
薬物療法と合わせて心理教育や認知行動療法などの心理的支援を実施することが望ましいです。
心理教育はクライエント本人や家族に向けて行われ、疾患の特徴や、服薬継続と休息の重要性、再発リスクなどを説明して理解を深めてもらうことを目的とします。
そして、認知行動療法によって極端な考え方を見直したり、客観的に自分の気持ちと向き合ったりすることを通じて双極症と付き合っていけるようにすることが重要です。
躁(軽躁)エピソードを呈する時期と抑うつエピソードを呈する時期は数ヶ月間継続することが多いですが、1年に4回以上という急速な頻度で状態が切り替わる場合は、急速交代型(ラピッドサイクラー)とよばれます。
短期間で病相が変動し、気分が高揚したと思ったらすぐに落ち込むといったことを繰り返し経験するのはとても苦しいことであり、本人だけではなく周囲の人もどのように対応したらよいかと苦慮しやすくなります。
双極症の人を支援するためには周囲の人の手助けが欠かせません。
家族や友人が今までとは異なる様子でひどく落ち着かない様子を見せたり、落ち込んだりしていることに気づいたとしたら、適切に休息を取るように促すことも有益です。
あまりに気分の変動が大きいようであれば医療機関の受診を勧めることが大切でしょう。