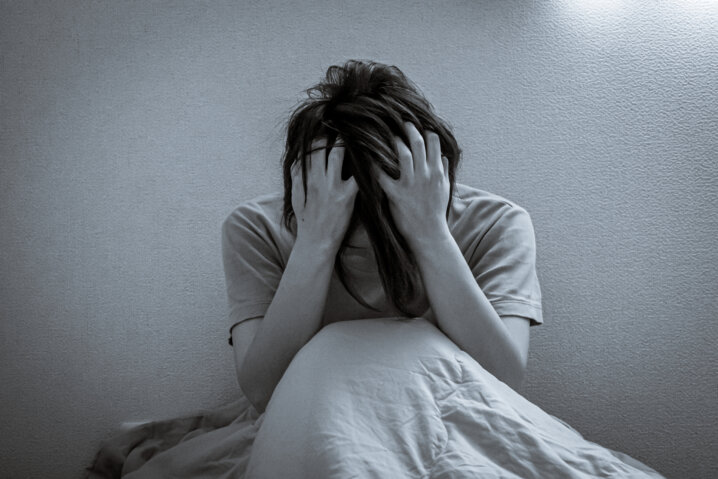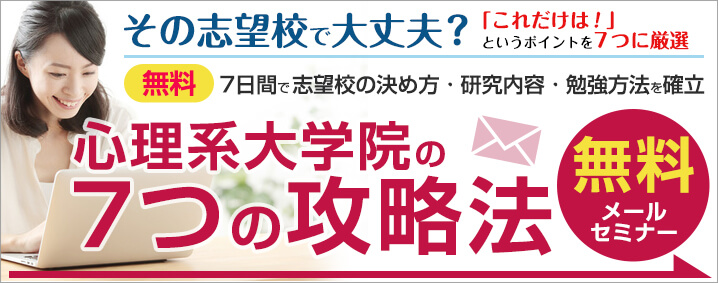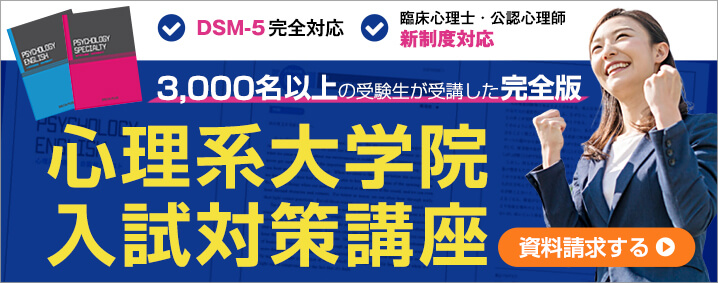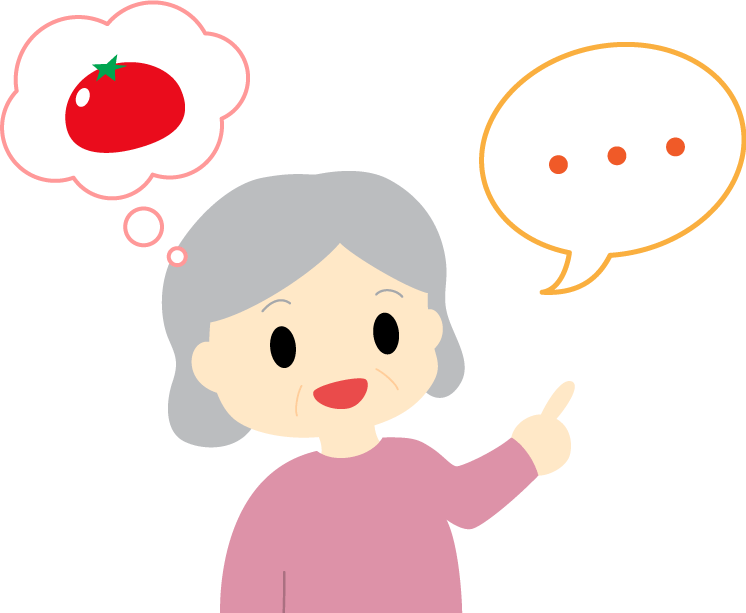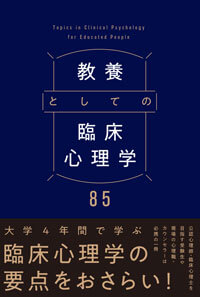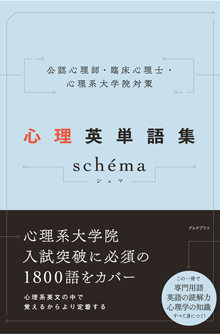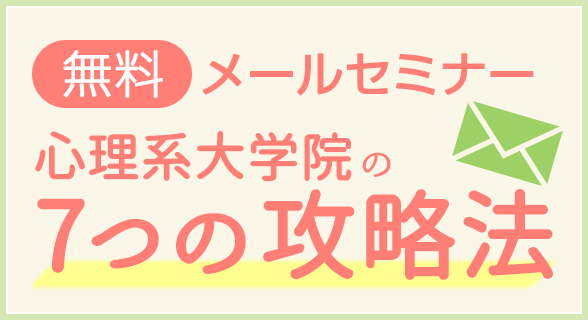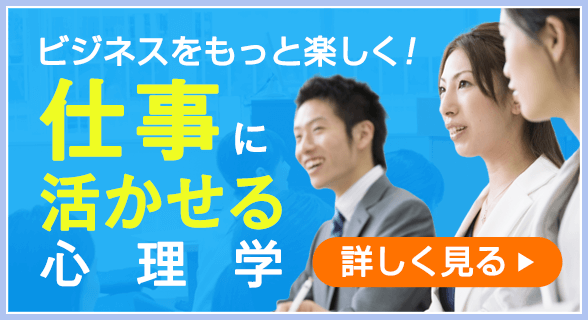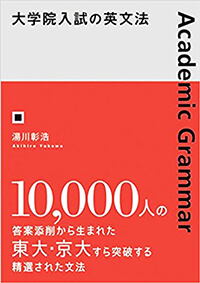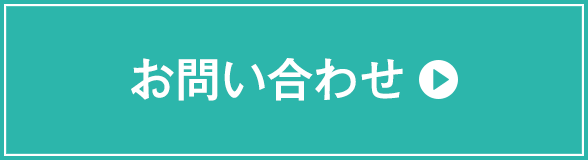統合失調症の定義
統合失調症とは、妄想や幻覚、まとまりのない会話などの症状を特徴とする、代表的な精神疾患の1つです。
現実検討力に大きな障害が生じるのが特徴で、自我の境界が曖昧になり、主観的世界に現実が支配されてしまう自我障害も大きな問題を引き起こします。
症状には大きく分けて陽性症状と陰性症状があります。
陽性症状は、通常、存在しないものが生じている状態で、具体的には、幻聴、妄想、作為体験などがそれに当たります。
陰性症状は、通常は備えられている機能が鈍ったり失われたりしている状態で、具体的には、感情の平板化、無気力、社会的引きこもりなどがあります。
陰性症状は、一般的に長く継続して残り、社会復帰の大きな妨げとなってしまうことが多々あります。
急性期には薬物療法が有効とされています。
侵襲性の高い心理療法は禁忌とされ、SSTや本人および家族への心理教育などが社会的適応を増すのに有効と考えられています。
急性期に陽性症状が顕著に現れ不安定な状態が続くと、妄想、幻覚、幻聴などの症状が強くなり、自傷他害の恐れが出てくる、自己管理ができず処方薬を正しく服薬できない、過度な妄想で社会生活を送ることが困難といった症状が見られることがあります。そのような場合に、精神科病院への入院が認められることがあります。
統合失調症は再発を繰り返すことで予後が悪くなるので、入院治療だけでなく、認知行動療法、SST、家族心理教育などを組み合わせて再発しないような関わり方をしていくのが望ましいとされています。
統合失調症の関連キーワード
- 現実検討力
- 自我障害
- 陽性症状(幻聴、妄想など)
- 陰性症状(感情の平板化、無気力など)
- ブロイラー,E.
- 精神分裂病
統合失調症の補足ポイント
統合失調症は、19世紀末、クレペリン,E.により「早発性痴呆」と呼ばれていたもので、後に、ブロイラー,E.が精神病理学的に捉え直しました。
日本では、それを直訳し、「精神分裂病」という名称が用いられていましたが、2002年、精神自体の分裂と誤解されやすいこと、患者の人格否定につながるなどの理由から「統合失調症」と名称が変更されています。
さて、統合失調症の症状について、もう少し詳しく見てみましょう。
幻聴は実際ない音が聞こえるものですが、統合失調症の幻聴は人の話し声である場合が多く、幻聴同士が会話をしたり、幻聴と会話ができたりする「対話性幻聴」であることが特徴です。
また、妄想については、盗聴器などが仕掛けられている、組織が自分を監視しているといった「注察妄想」、嫌がらせをされているといった「被害妄想」が多くみられます。
他にも、自分の考えが他人の声として聞こえてくる「思考化声」、自分の考えが人に知られてしまう「思考伝播」、人に考えを吹き込まれる「思考吹入」、誰かに操られているように感じる「させられ体験」など、自分と他人の境界があいまいになるのが、統合失調症の大きな特徴と言えます。
病識の欠如が統合失調症の特徴でもあるため、治療に結びつけることが難しいケースは少なくありません。
しかし、早い段階での適切な薬物療法により、人格の荒廃にまで至らず、デイケアなどの援助により社会生活を行えるようになることがあります。
そのため、プライマリケアからいかに早い段階で診断し、その後の治療へとつなげられるかが重要な課題と言えます。
統合失調症は一般的に、前駆期、急性期、消耗期、回復期という経過をたどります。
また、病状が落ち着いたかと思うと症状が再燃して入退院を繰り返す人もいれば、比較的順調に軽快して、服薬や作業所通所などを継続しながら安定した生活ができる人もいます。
症状が落ち着いてきたと思っても、ストレスにさらされることで急激に増悪する場合もあるので、油断せず治療を受け続けることが重要です。
治療は薬物療法を用いた医学的アプローチが中心になりますが、疾患に関する心理教育や作業療法、ソーシャル・スキル・トレーニングなども、QOLを高めるために有効な支援となります。