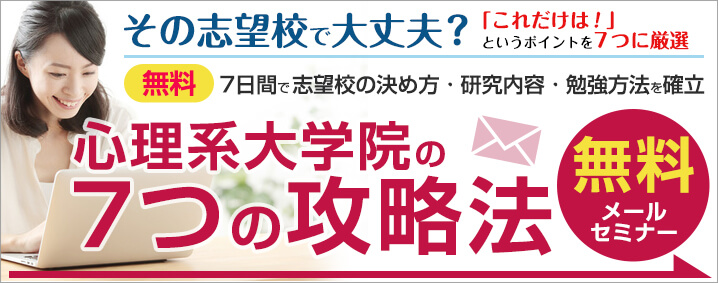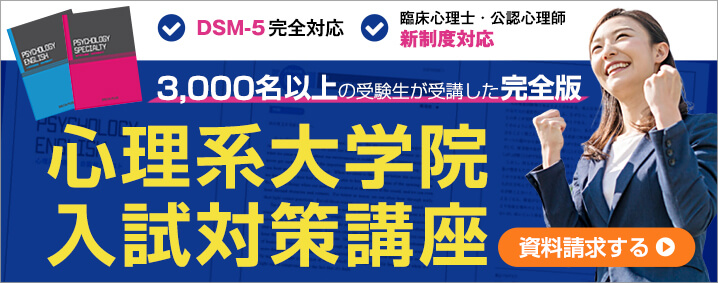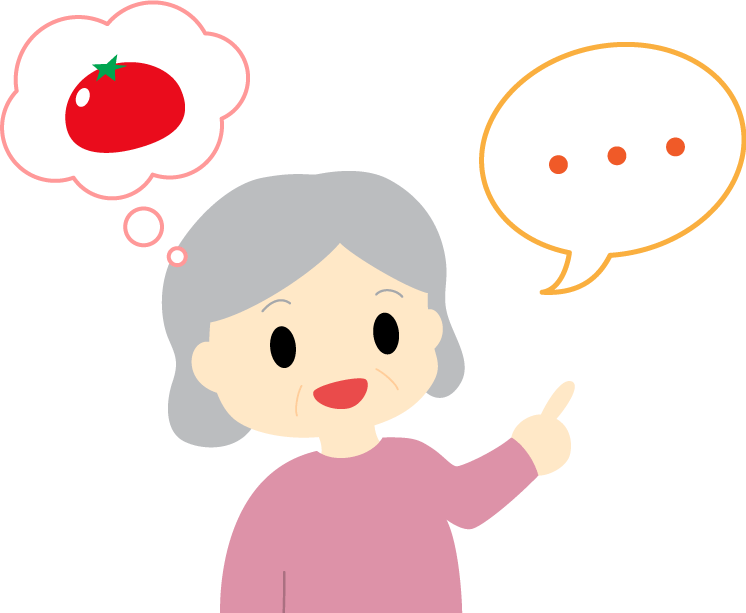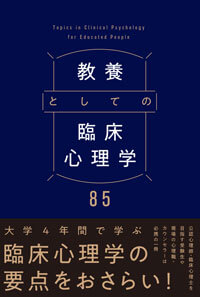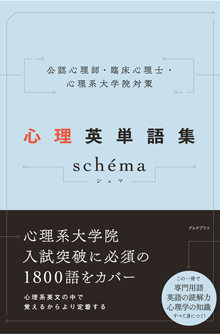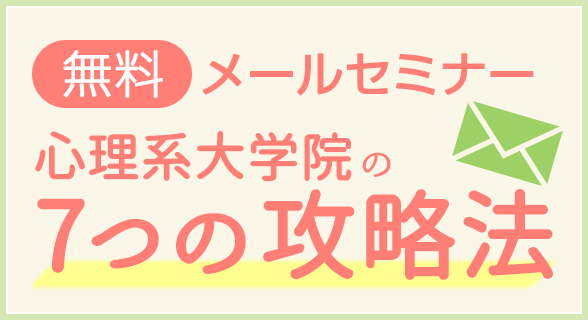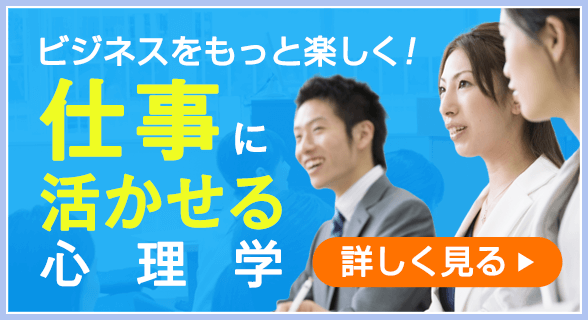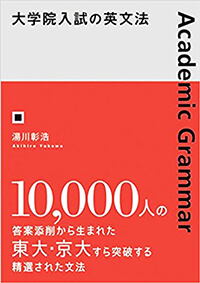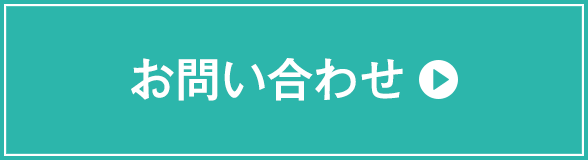パーソナリティ症の定義
パーソナリティ症とは、精神障害における分類の一種で、「人格障害」「性格障害」と記載されることもあります。
パーソナリティ症を持つ人は、ものの見方・考え方や、行動のありようなどが偏っており、その人が暮らす社会で一般的と考えられるあり方と極端に異なっているという特徴が見られます。
そうした特徴のために、日常生活に支障をきたして、本人や周囲の人が困ってしまう場合に医療機関に相談に訪れます。
パーソナリティ症の特徴として、感情をコントロールするのが苦手(情緒不安定)、自己・対人イメージが安定しない(対象関係の不安定さ)、極端な考え方をしやすい(全か無か思考)といった面が挙げられ、親子あるいは友人との間や、学校・職場などで対人的なトラブルを起こすことが多いです。
トラブルも一時的なもので終わるだけならパーソナリティ症とは言えませんが、環境やつきあう人が変わっても似たようなパターンでトラブルを繰り返してしまう場合は、トラブルを起こす根本的問題がパーソナリティに根差している可能性があります。
アメリカ精神医学会の診断基準であるDSMでは、パーソナリティの特徴ごとにパーソナリティ症を3つのカテゴリーに分類しています。
パーソナリティ症の関連キーワード
- 情緒不安定
- 対象関係の不安定さ
- 全か無か思考
- DSM
パーソナリティ症の補足ポイント
DSMでは、パーソナリティ症はA群、B群、C群の3つのカテゴリーに分けられています。
以下に少し細かく見ていきましょう。
A群は、疑り深く、他者の言動などに過度に敏感な猜疑性パーソナリティ症、感情的に冷淡で、人とあまり関わらないシゾイドパーソナリティ症、風変わりなものの考え方をし、人と深く関わらない失調型パーソナリティ症が含まれます。
B群は、社会的規範から逸脱し、そのことを意に介さない反社会性パーソナリティ症、感情の波が激しく、他者を感情的に巻き込むボーダーラインパーソナリティ症、他者からの注目を集めるために目立つ振舞いをする演技性パーソナリティ症、実際以上に自分が優れていると信じ、他者への共感性が欠如しがちな自己愛性パーソナリティ症が含まれます。
そしてC群は、他者との関わりを求める一方で、不安のため関わりを避ける回避性パーソナリティ症、必要以上に他者に頼りがちで、自身でものごとを決断することが難しい依存性パーソナリティ症、過度に几帳面なあまり、その几帳面さに縛られてしまう強迫性パーソナリティ症が含まれます。
パーソナリティ症は薬を飲めばよくなるというものではないため、心理療法に取り組み、自らのものの見方・考え方を見直し、再構築していくことが有効だと考えられています。
精神分析的精神療法や認知行動療法などさまざまなアプローチから研究が進められています。
DSM-5-TRから従来の「パーソナリティ障害」から「パーソナリティ症」への名称が変更されました。
中でも「境界性パーソナリティ障害」は「ボーダーラインパーソナリティ症」となり、今後はこちらの名称が使われるようになっていくことでしょう。
大学院入試ではB群の出題率が高く、特にボーダーラインパーソナリティ症がよく問われます。
理想化とこき下ろし、見捨てられ不安、衝動性の高さや自己破壊的な行動など、その特徴を一通り説明できるように押さえておきましょう。