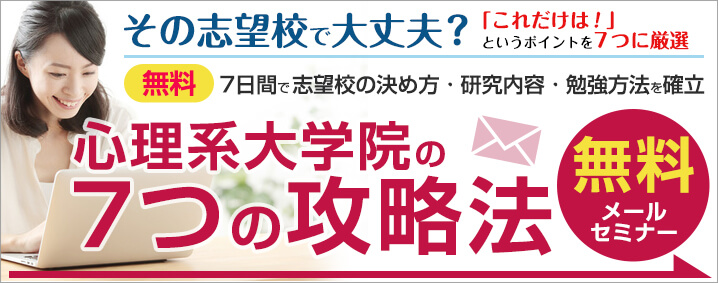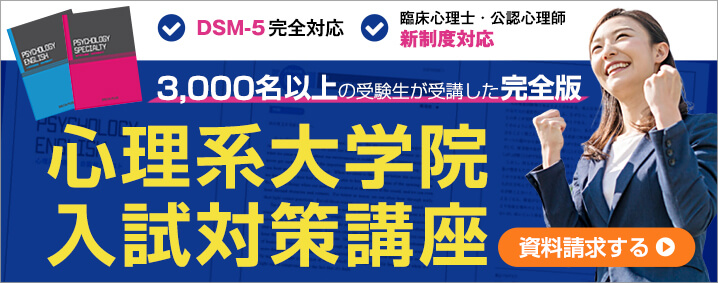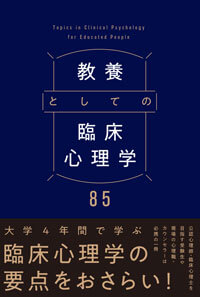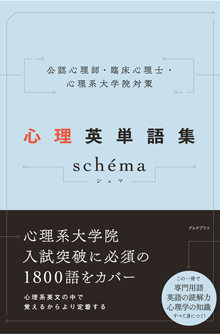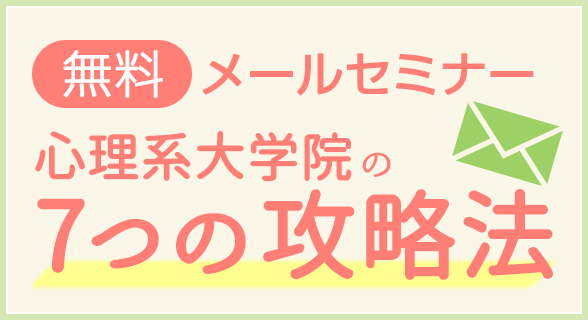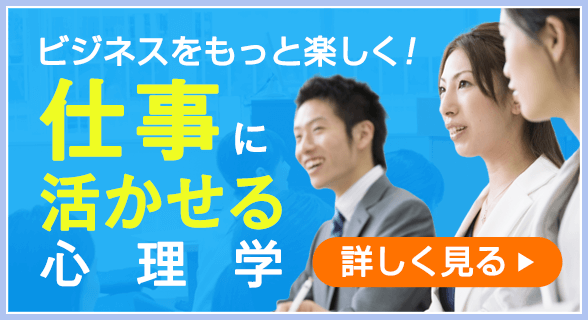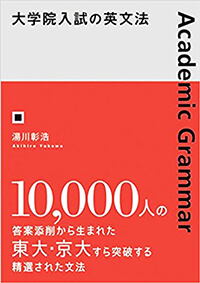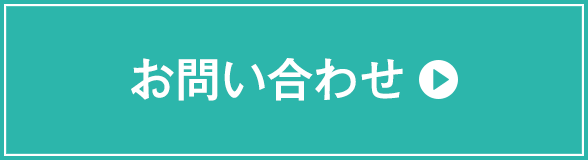自閉スペクトラム症の定義
自閉スペクトラム症とは、DSM-5の神経発達症群に分類される発達障害の一種です。
社会的相互反応における持続的な欠陥と、行動、興味、または活動の限定された反復的な様式を特徴としており、従来自閉症が持つとされてきた特徴を示す疾患群の総称です。
DSM-IVでは広汎性発達障害という分類があり、その中に自閉性障害やアスペルガー障害などが含まれていました。
しかし、ある人が自閉症的な傾向を示していたとして、その人の症状がどの程度であれば診断までできるのかを明確に決めることは困難です。
そこで、自閉症的な症状の強さをグラデーションやスペクトラム(連続体)として捉えるべきではないかという考え方がされるようになってきました。
こうしたスペクトラムという観点に基づくと、診断がつくほどではないもののこだわりが強いといった自閉症的な傾向が見られる人も、同じスペクトラムに含めて考えることができます。
自閉スペクトラム症の関連キーワード
- 社会的相互反応における持続的な欠陥
- 行動、興味、または活動の限定された反復的な様式
- 自閉症(自閉性障害)
- アスペルガー障害
- スペクトラム
自閉スペクトラム症の補足ポイント
自閉症という概念は、アメリカの児童精神科医カナー, L.が自閉症の定義を述べた論文を1943年に発表したことに始まります。
カナーが自閉症について取り上げた特徴が、長年にわたって自閉症の定義として広く用いられてきました。
その一方、オーストリアの小児科医アスペルガー, H.も、同時期に自閉的な児童についての論文を発表していました。
しかしアスペルガーが捉えた特徴は、カナーの定義とは若干異なるものでした。
カナーの論文は英語で、アスペルガーの論文はドイツ語で発表されたこともあり、カナーの説の方が世界的に広まり、アスペルガーの説はあまり注目されていなかったという背景もありました。
しかし、近年アスペルガーの論文が再評価されるようになり、彼が述べたような特徴を持つ人々も、広い意味では同じくカナーが言うところの自閉症というカテゴリーに含まれるのではないかと考えられるようになりました。
そして、カナー型の自閉症やアスペルガー障害、さらに障害とまでは言えないが自閉症的な傾向が見られる人々をスペクトラムとして包括して捉える観点につながっていきました。
自閉スペクトラム症の診断基準に挙げられている主症状の1つである社会的相互反応における持続的な欠陥の具体例を見てみましょう。
例えば、視線が合いにくい、一方的に話をする、冗談や抽象的な言い回しを理解しにくい、その場の空気や相手の気持ちを察して行動することが苦手といった形で表れます。
症状が比較的軽度の場合は、会話が時々噛み合わない、杓子定規、マイペースぐらいに思われることも多いですが、症状が重度になるとコミュニケーションが成立しない場面が増えるため、社会生活に支障が生じてきます。
行動、興味、または活動の限定された反復的な様式の具体例は、自分が好きなことには没頭するが、関心がないことには見向きもしない、自分のやり方に固執する、ルールを破る人を許せない、予定変更に上手く対応できないといったことが挙げられます。
症状が比較的軽度の場合は、頑固、融通が利かないという印象を持たれたり、正義感が強い、信念を持っていると見られたりすることもありますが、症状が重度になると協調性がない、自分勝手と周囲に感じられたり、周囲と折り合うことが困難になったりする場合が多く、やはり社会生活に支障が生じやすくなります。
これらの2つの症状は、DSM-5では3段階の重症度で評価されます。
自閉スペクトラム症の診断には、上記の2つの症状に加えて、生後12~24ヶ月頃の発達早期に発症し、こうした症状のために生活に明らかな支障が生じており、知的能力障害では説明がつかないことを確認する必要があります。
自閉スペクトラム症は、医師が症状や生育歴・発達歴などを問診して診断しますが、診断の有力な補助ツールとして心理検査が用いられることがあります。
例えば、AQ 日本語版自閉症スペクトラム指数という質問紙があります。
この検査は、成人用では本人自らが質問内容に回答し、児童用は本人の保護者が質問内容に回答することで、自閉症傾向を示す得点を算出します。
その他には、ウェクスラー式知能検査などの知能検査が用いられることもあります。
算出された知能指数そのものも参考に用いられますが、下位検査ごとの得点差に反映される認知的特性や能力の偏りに関する情報を客観的に確認するために用いられます。